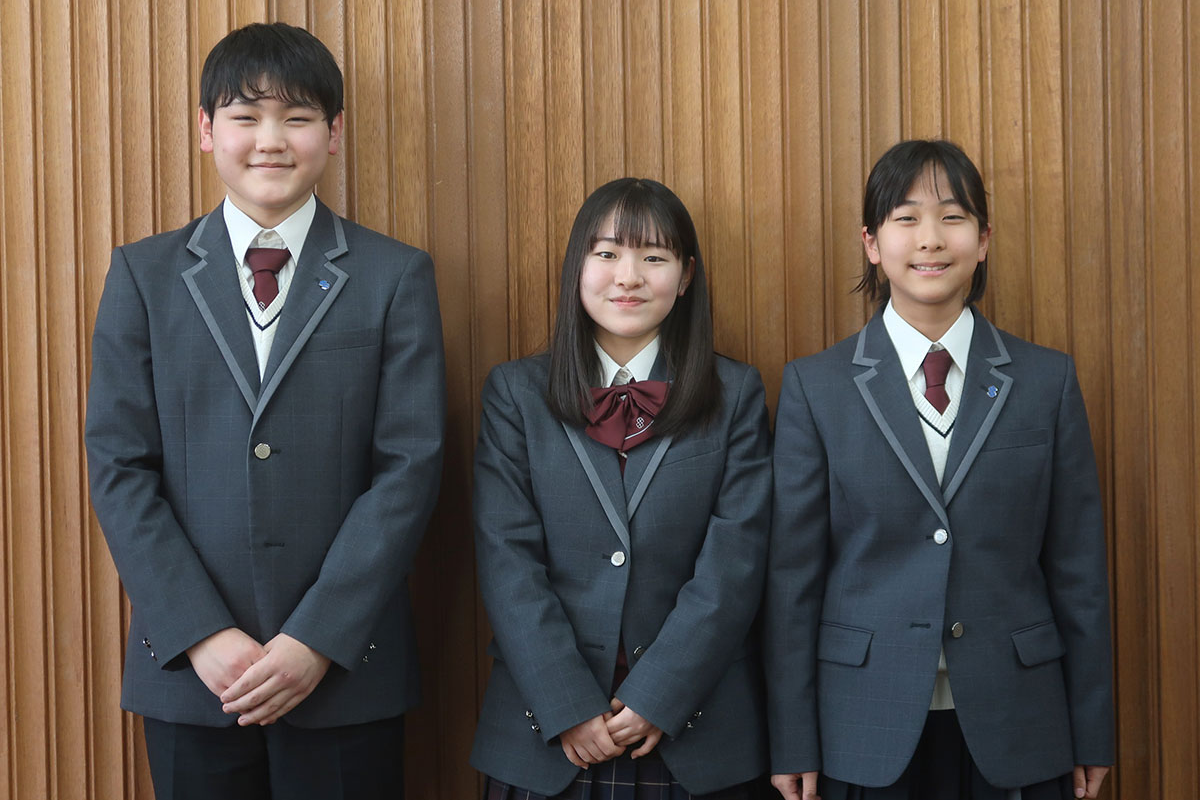学校特集
サレジアン国際学園中学校高等学校2025
掲載日:2025年4月1日(火)
「21世紀に活躍できる『世界市民』の育成」を教育目標に掲げ、2022年に共学校化と校名変更を経たサレジアン国際学園中学校高等学校。アップデートを重ねる同校の教育について、募集広報部部長の尾﨑正靖先生とインターナショナルコース部部長を務める英語科の久保 敦先生、広報委員でもある中1から中3の生徒たちに伺いました(生徒の学年はすべて2025年3月当時)。
包括的な環境で育まれる柔軟な価値観
「心の教育」、「考え続ける力」、「コミュニケーション力」、「言語活用力」、「数学・科学リテラシー」の5つを教育重点項目としているサレジアン国際学園中学校高等学校。大きな特徴は、すべての教科で課題解決型の学びであるPBL型授業を取り入れていることです。
募集広報部部長の尾﨑正靖先生は、中学3学年が揃った生徒たちの様子についてこう話します。

「教育目標の『21世紀に活躍できる世界市民の育成』へ着実に向かっている確信はあるのですが、コースを問わず生徒たちの個性が驚くほど多様だったので、その目標への向かい方が実に多彩であることを教わりました。
いい意味で広がりを持ったという感覚があります」
この多様さを表すひとつが中学校での、ゼミを通じて主体的に考え学ぶ「本科クラス」と、充実した英語環境で過ごす「インターナショナルクラス」に分かれるシステムです。インターナショナルクラスには、帰国生など高度な英語能力を持つ「Advanced Group(AG)生」と、英語学習に高い意欲を持つ「Standard Group(SG)生」がおり、互いに刺激し合いながら過ごしています。
さらに中1では本科生、SG生、AG生を混在させた「ハイブリッド学級」を編成。様々なバックグラウンドを持つ生徒たちが同じ教室に集うことで、より多彩な人間関係を築けるベースとなっています。
このハイブリッド学級と中2以降のインターナショナルクラスは、日本人教員とICスタッフと呼ばれる外国人教員によるダブル担任制を取っており、HRなどはすべて英語で行われます。ハイブリッド学級の導入により、校内の雰囲気はどう変わったでしょうか。

尾﨑先生「1学期は日本語の補足が必要だった本科やSGの生徒ですが、3学期になるころにはおおよその日常会話は英語で理解できるようになっていました。
本科生やAG生の英語力の伸びも素晴らしいのですが、SG生の伸長率は特に目を見張るものがあります。元々英語が好きで入学したSG生たちは、週10時間の英語授業やAG生と共に過ごす環境で急激に成長しています」
なお、コロナ禍に開校したため、海外へ出る計画が立てられず、当初はオンラインで海外の姉妹校などと繋がっていた同校。2023年度からは徐々にリアルでの海外交流を叶えています。中2から高2までの希望者参加型で夏にオーストラリアで行われる「スタディツアー」は、23年はクイーンズランド、24年はメルボルンで実施されました。25年度はパースで開催される予定です。
世界97ヵ国に広がる姉妹校のネットワークを生かしながら、毎年行く場所や体験内容を変え、英語がもっと好きになる仕掛けや異文化に触れる機会を用意して、より広い視野を培っています。
生徒たちの知的好奇心を大きく刺激するのは、もちろん英語環境だけではありません。
尾﨑先生「本科生は中2以降、ゼミに入り自分の研究に打ち込み始めていて、その経験をインターの生徒たちにも共有してくれています。よりアカデミックな部分で深く繋がることができ、校内の雰囲気はさらに良くなっています」
互いの学びが充実するほどに教え合ったり切磋琢磨し合ったりできる環境が整っているサレジアン国際学園。生徒たちは世界の多様さや複雑さについて、肌で感じながら学び、考え抜き、実感を伴いながら邁進しています。
本科生が語る、サレジアンの魅力
本科クラスに所属する中2のG・Nさん。自身がサレジアンに入ってどう成長したかを伺いました。

G・Nさん「PBL型授業を通じて、人との対話が比較的得意になってきたと思います。話せるようになったきっかけは、中2の3学期に国語で行われた『常識とは何か』をテーマとした授業です。ひとつの事柄について、昔から常識とされていることと新説を知り、自分自身でも考え、他の人の意見もたくさん聞くことで物事を多角的に見る重要性を学びました。
最初の頃、みんなと同じような意見になりがちだったり、先入観に捉われてしまったりということが僕自身の課題だと感じていました。
中2の夏に参加した『スタディツアー』で現地の文化に触れたことによって、自分の主張を伝える大切さをよく考えるようになりました。
サレジアンでは自分自身を含めて、それぞれの考えをきちんと伝え、尊重し合う経験を重ねています」
本科生は先述の通り、中1のプレゼミを経て、中2から高2までゼミナールで個人研究を行います。
G・Nさん「Entrepreneur養成講座で学んでいます。研究テーマは社会課題であればOKです。将来は国のために自衛隊で働きたいと思っています。そのため、制度に反対する人たちともうまく関わっていくための方法を研究しています。
この講座を選んだのは、見学の時の先輩方のプレゼンがとにかく楽しくて、聞きやすかったから。ここに入って自分もプレゼン上手になりたいと思いました。
実際にプレゼンをしてみると、自分が想定していなかった方向から質問が飛んでくることもあって難しいことも多いですが、楽しいこともたくさんあります」

G・Nさんが心がけているのは、プレゼンの際に図や情報の取捨選択を冷静にすること。ゼミで学んだ1年間でその先輩に追いつきましたか?と聞くと「少しは追いついたのかな。よくわかりません」とはにかみます。
こんなことも教えてくれました。
G・Nさん「同じゼミの先輩がK-POPにおける、徴兵時の経済的な損失について研究しています。自分にはなかった視点でした。
他のゼミに所属する友達は、フルーツで美容液を作ろうと研究しています。最初に聞いた時はすでに商品化されているのでは?と思いましたが、いざプレゼンを聞いてみたら、成果としての美容液ができていて、挑戦することの大事さを考えさせられました」
最後に、広報副委員長になった理由を教えていただきました。
G・Nさん「自分の好きな部分を紹介したいと思いました。学校説明会ではボランティアとして参加していますが、他の委員会とはまた異なる強みや人と話す力が身につくのではと考え希望しました」
SG生が語る、サレジアンの魅力
インターナショナルクラスでSG生として学ぶ中1のM・Mさん。サレジアンに入学した時点での英語力はどの程度だったのでしょう。

M・Mさん「普通の公立小学校で学んだくらいの英語力でした。それでもSGで学びたいと入学したのは、国際系の学校に通っている姉の存在が大きく影響しています。困っている外国人に英語で対応している姿がすごくかっこよかったんです。私も英語を使いこなせるようになりたいと思いました」
実際の学校生活はどのようなものなのでしょうか。
M・Mさん「ICスタッフの先生がたくさん話しかけてくれます。会話するのが楽しくて繰り返していたら、自信を持って人前で少しずつ英語が話せるようになってきました。
クラスにはインターナショナルスクールに通っていた人や外国から来たばかりで日本語がまだ苦手な人など、いろいろな背景を持つ友人が揃っています。
外国にルーツがある子たちは自分の意見を率直に話しますし、ユニークな発想を持っています。PBL型授業の時に自分では思いつかなかったような考え方を伝えてくれてとても刺激的です。ハイブリッド学級は多様な価値観が混ざり合っていて、日々の発見があり豊かです」
1月には英検3級に挑戦し、見事合格した頑張り屋さんのM・Mさん。でも実はいちばん好きなのは国語の授業と教えてくれました。

M・Mさん「PBL型学習のトリガークエスチョンがすごく深くておもしろいんです。例えば1学期には『椅子はなぜ椅子だとわかるのか』、『生成AIは考えているのか』などを考えました。
今は構造主義を学んでいますが、ソシュールなどの歴史人物を知ることができたり、外国語と日本語を比べたり、日々使っている言葉に対して疑問に思ったり、たくさん考えさせられる授業で楽しいです」
最後にサレジアン国際学園の魅力を伺いました。
「優しくておもしろい先生が多いことです。各教科の先生も個性的で、例えば数学を心から愛しているような数学の先生や幅広く深い知識がある国語の先生など、ひとりの人間としても教師としてもかっこいい先生方がいて憧れます」
AG生が語る、サレジアンの魅力
AG生としてインターナショナルクラスで活躍する中3のE・Fさん。小学校までインターナショナルスクールに通っていて、元々は日本語が得意ではなかったと言います。

E・Fさん「実は緊張してしまう性格なので、人と話すのはあまり得意ではありませんでした。しかしサレジアンでは、人とコミュニケーションを取ることが日常的に多いのです。話してみたらとても楽しいと思えるように変わりました」
プレゼンテーションやディスカッションを行う機会が多い同校での生活。E・Fさんは、中1・中2の時は調べた情報と意見を単に説明して終わりという普通のプレゼンをしていたと話します。
E・Fさん「中2の後半からはTEDトークを意識して、情報を正確に伝えることや自分の意見を楽しみながらプレゼンできるような研究を始めました。自分の思いを伝えるという面では英語力も向上したと思います」

E・Fさんは2024年度の学園祭で企画を持ち込み、すべての交渉などを含め、自分たちで成し遂げました。そのきっかけはなんだったのでしょう。
E・Fさん「iTimeというインターナショナルクラス独自の国際探究の時間があります。この授業のおかげで考える楽しさを実感し、知識が深まり、発想が広がる体験をたくさんしました。その経験を他の人にも体感してほしくてiTimeを軸に何かできないかと考えました。先生方に相談したところ、オーストラリアの姉妹校とのオンラインディベートを実現することができました」
姉妹校との交流を通じて気づいたことには何があるのでしょう。
E・Fさん「表現の違いから、彼らは日常的に意見を述べ合う会話をしているのだろうと感じました。私たち日本人からは、自分の考えを伝える大切さと共に人への気遣いも感じられました。考え方をリスペクトすることも、それぞれの文化を尊重することの大切さも同時に学べて良かったと思います」
高校では、慎重かつ活発に様々な挑戦を楽しんでいきたいと話すE・Fさん。「サレジアンは自分らしくいられる環境です」と教えてくれた笑顔が弾けます。
年々パワーアップするサレジアンの教育

多様な個性が行き交い、様々なチャレンジを支える同校の教育は日々、アップデートを重ねています。
インターナショナルコース部部長の久保 敦先生に伺いました。
「2026年1月からスタートするプログラムが、西オーストラリア州政府の高校卒業資格である『WACE(Western Australian Certificate of Education)』です。
西オーストラリア州と日本の高校両方の卒業資格が取得できます」
久保先生は昨年、このWACEプログラムに対応したパースでの留学システムを構築してきました。もちろん留学せずに日本にいながらWACEを受けることも可能です。
なお、「Dual Diploma Program(DDP)」により、海外の高校卒業資格も取得できるカリキュラムもすでに敷いている同校。アメリカの「College Board」で、レベル1という最上位に認定されています。
日本の一条校がこれらの認定を受けるには高いハードルがあります。同校はインターナショナルスクールレベルの教育が担保されているからこそ、これらの導入が可能となっています。
久保先生「『College Board』の高大接続プログラムである『Advanced Placement(AP)』を本校で展開できるようになります。
この『AP』の試験やアメリカでの大学進学における標準テストである『SAT』が校内で受けられます。これにより、トップ級のアイビー・リーグにも挑戦できると思っています」

「WACE」ではオーストラリアやニュージーランド、イギリスを、「College Board」ではアメリカをカバー。AGだけでなく、SGや本科の生徒にとっても海外へ目を向けやすい環境です。br>
なお、インターナショナルクラスで教鞭を振るうICスタッフは、6か国の出身者16名が在籍。数学や理科、社会の授業を英語で展開しています。多様な出身国から集まる彼らは、授業だけでなく行事などでも、様々な提案をしてくれるそうです。
久保先生「ICスタッフは、マスターまで英語で学んだ経歴を持ち、教員免許を持っていて指導歴は5年以上を条件としています。ナイジェリア人の数学の先生もいますが、生徒たちは英語も多様であることを理解できるでしょう」
さらにAPの指導経験を持つ先生なども増える予定で、4月以降は計24名のICスタッフが授業を行います。
学校全体に多様性がより広がり、実感を伴った成功体験を積み重ねながら成長するサレジアン国際学園での生活。学園祭や学校説明会など、在校生たちの輝きを目撃しに足をお運びください。